神戸市水道サービス公社労働組合
「不当労働行為救済申し立て」地方労働委員会闘争
兵庫自治労連書記長 森栗 強
7月20日不当な「命令書」
神戸市水道サービス公社労は、一昨年の2002年マイナス人勧に伴う、当局の強引な賃下げ攻撃に反対し、昨年7月に兵庫県地方労働委員会へ、水道サービス公社と神戸市水道管理者の行いを「不当労働行為」として「救済申立」を行い1年の間地労委闘争を続けてきました。
一年間の闘いの末、本年7月21日に地方労働委員会より「命令書」が出され、残念ながら、私たちの主張を全く取り入れない、棄却・却下と言う不当な命令書になりましたが、この地労委闘争を通じ、当局の攻撃の不当性が労働者の前に明らかになり、組合員も7名から50名に組織拡大され、労働者代表の選挙につていも当局と連合労組が一体となって推す候補者を破り神戸市水道サービス公社労委員長が組合員数の2倍もの109票を獲得し圧倒的勝利をするなど、組織的に大きな成果を得、掲示板の設置など当局との力関係も変化を見せています。
組織拡大の中での闘い
2002年の人事院勧告において初めて本俸部分がマイナスになり、約2%賃下げ勧告が出され、さらに神戸市では一般職員の賃金を4%一律削減も決められており、合わせて約6%もの賃下げが強行されると言う状況下から闘いが始まりました。
人事院勧告も一律賃下げも一般職員に対しての措置・制度であるにも関らず、それらの大幅賃下げを不安定雇用・そしてなによりも極めて低い賃金の嘱託職員である水道メーター検針員、しかも水道局の外郭団体にまで、押し付けてくると言う不当な合理化が強行されました。
私たちは当然交渉も重ね、神戸市の財政運営の問題点を始め、大幅賃下げの不当性を追求しましたが、当局は神戸市の財政難は「オール神戸での対応」また「水道局からの委託料の削減」の賃下げ理由しか述べず、水道サービス公社としての、独自の判断・努力を見せずに、私たちの反対を押し切り大幅賃下げを強行しました。
2002年の年末から、申立を行なうまでの約半年間で、当該労組での大きな、組織的な大きな前進がありました。大幅賃下げの労働条件変更にさいして、過半数を占める組合がないため労働者代表の選挙を行う必要があり、当局の自作自演で労働者代表の信任選挙がおこなわれました。この選挙には当局と「癒着」をしている、公社の正規職員だけで組織されて「連合」全水道労働組合の役員が立候補しましたが、2度の信任選挙を、当該の自治労連の組合員、7名(当時)の口コミなどの奮闘によって、2度とも「不信任」とさせる事ができ、この事が、「反対は反対の声を上げる」「当局の好き勝手にさせない」、との意気込みが職場全体に広がり、嘱託検針員約140名のうち、またたく間に40人近くにまで組織の拡大が進み、この時点で、7名から組合員の5倍化に成功をしました。
このような、組織拡大の実績と、労働組合の基本を始め様々な学習を重ね、当該の組合員の意気込みによって、地労委闘争の決断をしたという経過があります。
当初は「ニュースはどうして作るの」「執行委員会て何?」から始まり、今では不定期ながらニュースの発行、そして何より「過半数の労働組合になろう」、「一人でも組織拡大を」との意識が高まり、地労委の証人尋問も二度、行なわれましたが、それまで組合加入を隠していた人も含めて、それぞれ30名近い動員を行なう等、元気ある闘いが進められました。
「これからの闘いへ意思統一」
「命令書」では却下したものの、神戸市が「公社に対して影響力を有していることは否定できない」と明言しており、今後も神戸市に対して、賃金だけでなく様々な問題について行動を起こすことの出来る内容にもなっています。
さらに団体交渉については「使用者は、組合に対して譲歩できない事項についても、自己の主張を組合が理解し、納得することを目指して、その主張の根拠を具体的に説明するなど、誠実に対応しなければならない」とも明記しています。様々な攻撃に対しても、粘り強く交渉を求めれば当局は応じざるを得なくなり、これから「民間委託」を始めとした様々な攻撃との闘い方の方向性が明らかにされた内容になっています。
当該労組では、今回の地労委闘争を通じ、今までに出来なかった様々な経験をし、また一企業内での、力関係・感情だけで賃金が決定されるのでなく、今の労働者・国民犠牲の小泉「構造改革」、規制緩和などの国の政治と、市民より神戸空港などに代表される大企業優先の神戸市政が、労働者の労働条件に大きく関ることも肌身で感じ、悪政に怒りを覚え、さらに兵庫県における地方労働委員会の矛盾に対しても大きな疑問を持ち、その怒りと疑問をこれからの闘いの糧にすることが意思統一されています。
「命令書」の棄却・却下に屈することなく、引き続き闘いを進める事と一人でも多くの組織拡大を決意しています。
今回の地労委闘争では、山内弁護士・白子弁護士に闘いの指導を始め様々なご指導を頂き、地労委での証人尋問での追及は、傍聴をした多くの組合員が感嘆し、感動覚えるほどの鋭い内容でした。お二人をはじめ、ご支援を頂いた多くの皆さんに心からお礼を申し上げます。
このページのトップへ神戸市水道サービス公社労働組合「声明」
|
2004年8月2日(月) 兵庫自治労連第14回執行委員会 |
|
| 却下の命令でも神戸市の運営責任と誠実団交義務認める(声明) | |
| 1.不当な命令 2004年(平成16年)7月21日付で、兵庫県地方労働委員会は自治労連神戸市水道サービス公社労働組合(以下「組合」という)に対して、(財)神戸市水道サービス公社(以下「公社」という)と神戸市に対する不当労働行為救済申立てをそれぞれ棄却、却下するとの不当な命令書を送ってきた。 2.経過の概要 組合が、公社や神戸市を相手に不当労働行為救済申し立てを行った経緯の大要は以下のとおりである。 (1)2002年(平成14年)12月、公社は「就業規則の改定について」の通告を、組合員ら検針業務員に対して行った。その内容は①2003年(平成15年)1月1日より、「基本報酬」と「賞与」のカット(これによって、約1.66%の賃金カットになる)、②同年4月1日より、「基本報酬」の約4%のカット(先のカットと合わせて、約5.66%=約1万円のカットとなる。なお、改定前の平均賃金は賞与分を含んで、約17万6千円である)、というものである。 (2)上記、公社の通告内容の2003年1月1日からの賃金カット1.66%、同年4月1日からの賃金カット4%という数字は、給与条件の全く異なる神戸市の正規職員のカット率をそのまま押し付けたものであり、そもそも賃金総額の低い嘱託検針員の被る打撃の大きさを全く無視した不当なものである。組合は納得せず憤りをもって、2002年12月10日、同月25日、2003年2月19日、同年3月7日と計4回の団体交渉で撤回を要求した。 (3)ところが、公社は①神戸市・水道事業管理者との「委託契約」で人件費を賄っている、②神戸市が人件費を削減してきたらその範囲内でしか支払えないとの答弁を繰り返し、神戸市の指示通りに給与改定を行うしかないとして、通告内容どおりに就業規則の不利益変更を強行した。 (4)公社側交渉委員が、組合との団交の場でも自認し、度々弁明していたところでもあるが公社は、法人格こそ神戸市から独立しているものの、両者の「委託契約」の内容は、神戸市が一方的に決定し、委託料の内訳である人件費も神戸市が一方的に決定している。公社はおよそ労使交渉における独立した裁量権限を有しているとは思えない。 したがって、誠実な団体交渉を行うには、公社が独立した裁量権限を確保して臨むか、あるいは神戸市の権限ある担当者がともに交渉に臨むべきであるにもかかわらず、公社等はそのようにはしなかった。極めて不誠実な団交の対応である。これは、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むこと」(労働組合法第7条2号)に該当する不当労働行為である。 (5)次に、このような公社側の不誠実対応の交渉継続中に、契約更新時期が到来し、組合員である検針員が自己の労働条件について、「労使合意に至った時点でその内容を変更することを条件として契約更新する」旨の意見を付して、主張を行うのは当然の権利というべきである。これに対して、公社が条件付の契約更新には応じられないとして意見書の受け取りを拒否し、契約更新を拒絶する旨の言動を行うなどは、組合活動を規制し、自主運営に「支配介入」(労働組合法第7条3号)する恫喝とも言うべきものである。 (6)このような経緯があって組合は、2003年(平成15年)7月1日、兵庫県地方労働委員会に対する不当労働行為救済申立てを行ったものである。 3.救済請求内容 (1)公社や神戸市は、組合から申し入れた賃金に関する団体交渉に誠実に応じること。 (2)組合の自主的運営に支配介入しないこと。 (3)不誠実団交と更新拒絶を手段として組合の自主運営に支配介入したことの謝罪文を掲示すること。 4.争点と命令の問題点 (1)地労委は本件の争点として1.神戸市に使用者性は認められるか、2.公社と組合との間で行われた団体交渉は、不誠実な団体交渉に該当するか、3.公社が組合員から提出された意見書の受け取りを拒否したことは支配介入に該当するか、を挙げている。 地労委の判断は結論を先に見ると、1.神戸市の使用者性について、公社の運営面に対して影響力を有していることは認めるが、従来から公社と別労組(「全水道公社組合」のこと)の交渉で賃金等決定しており、神戸市の関与は認められないという表面的な判断から市の使用者性は認められないと結論付けている。 次に2.不誠実団交に該当するかという点については、使用者は自己の主張を組合が理解し、納得することを目指して、その主張の根拠を具体的に説明するなど、誠実に対応しなければならないとしながらも、公社に「独自の交渉権限」の枠が大きくあるかのように見て、公社が資料を用いた説明を繰り返し行っており、2003年3月7日以降組合からは団交申し入れもなかったから、不誠実団交には当たらないという。最後に3.意見書受け取り拒否については、非組合員が含まれていたとはいえ、19名もの意見書を組合の行動とはみなさずに、一部の嘱託職員との「条件付の労働契約」の締結は好ましくないという一方的な公社の意見を採用して、これまた組合に対する支配介入には当たらない等々、悉く組合の請求を認めない内容である。 (2)今回の地労委の命令には幾多の問題点を含んでいる。地労委の争点にも挙がっているわけではないが、公務員賃金(ここでは神戸市職員の賃金)の決定問題が背景にあることを地労委の委員、とりわけ労働者側委員は職責からも見落としてはならない。公社が賃金カットを提案した2002年は、人事院が人勧史上初めて、基本賃金マイナス2.03%、7,770円という基本賃金引下げの勧告を行った年である。しかも人事院の勧告は、「基本賃金の引下げ」を実質、4月に遡って実施するという不当なものである。人事院勧告が、労働基本権剥奪の「代償措置」と主張するのなら、マイナス勧告や、ましてや「不利益不遡及」という「法」の根本原則を犯す行為は、二重三重の誤りを人事院が犯すものであり、この勧告は到底認められないとする多数の公務員組合からの抗議声明が続出したことは当然である。現にその後、法廷闘争を行っている、公務員組合も現にあるのである。 このような人事院勧告に追随した形で、神戸市人事委員会も2002年9月6日、基本賃金マイナス1.73%、7,906円の基本賃金引下げという、人事院勧告に準じた4月遡及の勧告を行い、関係する労働組合との労使交渉を行うことになったものである。 公社は史上初の基本賃金引下げという、神戸市人事委員会の勧告による神戸市職員の交渉結果を受けて従来と同じく当然のように、前掲別労組(全水道公社組合)に対して、神戸市と同じ内容の給与引下げ提案を行ったものである。 ここは大事な点である。地労委はいかにも、公社が独自の権限で賃金労働条件を決定しているかのように判断しているが、公社の提案時点から、地労委の命令書自身、「市と同じ内容の給与引下げを提案し」と明記しているように、神戸市追随で提案自体が独自性を発揮しているといえないのは明白である。 次に、人事院の勧告は国家公務員の一般行政職を対象とし、神戸市の人事委員会勧告も一般行政職員が対象である。にもかかわらず、公社職員についてまで神戸市職員と同様の提案を、これまた当然のように行っていることから見ても、公社の独自性には疑問ありと言わざるを得ない。労働基本権なかんずくストライキ権を剥奪された公務員組合(この場合は神戸市職員労組)がやむなく妥結した内容を、公社職員に同一内容で提案を行っているところに寸分の独自性もあるとは言えない。 (3)次に最大の問題点は、①神戸市は公社の基本財産の全額を出資していること、②公社の収入の約9割は、神戸市からの委託料によるものであること、③委託料は年度末に過不足が神戸市と精算されるものであること、④公社の役員及び管理監督者の多数は、神戸市の退職者や市からの派遣職員であること、等々を判断して神戸市が公社の運営面に対して影響力を有していることは否定できないとしながら、直接交渉の矢面に立ったことはないことでもって、神戸市の使用者性を否定していることである。 労働契約上の使用者ではないが実際上それに近似した地位にある企業も不当労働行為を禁止される「使用者」と認められる。例えばある二つの企業が親子企業の関係にあり、親企業が子企業の業務運営や労働者の待遇につき支配力を有している場合に、親企業が子企業の従業員に対し「使用者」(労組法第7条)の地位にあるとされる(菅野和夫「労働法」第6版649頁)。すなわち、親会社が株式所有、役員派遣、下請関係などによって子会社の経営を支配下におき、その従業員の労働条件について現実かつ具体的な支配力を有している場合には、親企業は子企業従業員の労働条件について子企業と並んで団体交渉上の使用者たる地位にある(前掲書同頁)。 公社は、神戸市の業務の一部門である「市内における水道の円滑な利用の促進と適性かつ合理的な維持管理のために必要な事業」を行うことなどを目的として設立されている。同時に上記に列挙された内容は全て、運営責任だけでなく神戸市の使用者性を証明するものとなっている従来から団体交渉に神戸市として出席していないことや、出退勤の管理等を行っていないこと等をもって使用者としての団交出席義務を免れることはできない。 (4)組合員である嘱託職員等の人件費が神戸市からの委託料で賄われていることは命令書に明記されている。しかも委託料は年度末で過不足を神戸市に対して精算することになっており、その意味では連結決算されているのである。これらの事情を資料を用いて繰り返し詳細に説明したからといって、組合が理解し、納得しない限り団体交渉を誠実に行ったことにはならないことも命令書は明記している。組合が団交の進捗状況を見て不当労働行為として地労委への救済申立て準備を優先し、団交の申し入れを行わなかったことまでも理由にして公社の姿勢を擁護することは、地労委の労働者救済の役割放棄といわざるを得ない。 (5)最後に、争点の3番目の組合への支配介入について言えば、労働者が自らの権利擁護のために、使用者に対して処遇要望を行うのは当然であり、言論・表現の自由である。しかも、意見書提出は労働者にとって瞳のごとく大事な団結権の行使であり、労働組合としての意思表示にほかならない。これを、敵視するごとく一部の嘱託職員の個人的意見書として矮小化すること自体、組合否定の不当労働行為である。 5.成果と今後の対応 (1)地労委は組合の申立てを不当に棄却、却下したものの、使用者は、組合に対して譲歩できない事項についても、自己の主張を組合が理解し、納得することを目指して、その主張の根拠を具体的に説明するなど、誠実に対応しなければならないことを明記している。これは当然に公社にも適用される指摘である。また、神戸市の使用者性は認めなかったものの具体的な事実を列挙して公社の運営に対する影響力を認めている。この点で運営の責任を組合は今後、神戸市に対して追及する根拠を得ることが出来たのは大きな成果である。 (2)神戸市水道サービス公社は、地方公営企業として公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。廉価で安全・安心の給水事業を行うためにも誠実な労使関係の確立は重要である。組合は、神戸市民の福祉増進の観点から引き続き職場環境の改善、働く労働者の賃金労働条件の改善をともに追求していくものである。 |
|
このページのトップへ
第42回総会報告
弁護士 萩田 満
2004年9月4日)、神戸酒心館(神戸市東灘区)において民法協第42回総会が行われ、のべ34組合・団体、53人が参加した。
1 記念講演「憲法改悪の現段階」
神戸学院大学・大学院 実務法学研究科 上脇博之(かみわきひろし)教授(憲法学)
(1)今回の記念講演は、緊迫化する憲法「改悪」の動きについて、上脇先生の講演であった。
上脇先生の講演の趣旨は、特に9条改憲に賛成する国民の一部は専守防衛のために自衛隊が必要ではないかと漠然と考えているが、自公民各政党、財界、アメリカが目指しているものは、専守防衛だとか国際貢献を目指したものではないことを分かってもらう必要がある、ということにある。
(2)そこで、まず古典的改憲論(押しつけ憲法論)の現代的意義の説明があった。押しつけ憲法論とは、現行憲法が、敗戦後に占領国であるアメリカによって憲法が作られたものであり、天皇主権の明治憲法への回帰を主張する論調である。こうした押しつけ憲法論は、国民主権を奪うことになるので到底国民には受けれ入れられないとともに、現在の改憲論がアメリカに言われたものであるから「アメリカ押しつけ」ということは自己矛盾を来すことになるので、なりを潜めている。
その後の解釈改憲は、国民世論を反映して、名目上は「専守防衛」に徹すると言わなければならないものであったこと。しかし、1991年の湾岸戦争やカンボジアPKOを機にいっきに専守防衛の枠組みを超えていこうとしている動きが顕著になっている。
(3)とりわけ、90年代後半以降は、日米安保共同宣言や新ガイドラインにあわせて、次々に自衛隊によるアメリカ支援が拡大している。ここで、狭義の有事法制と、広義の有事法制とを考えてみなければいけない。まず、狭義の有事法制とは、昨年から今年にかけて成立した有事関連法や国民保護法という枠組みであり、これは有事(戦争)のときの国民動員体制を整備することと「武力攻撃のおそれ」があると政府が認定するだけで発動できるという点が重要である。これに対して、広義の有事法制とは、新ガイドライン関連法、同時多発テロ以降のテロ対策措置法、イラク戦争後の特別措置法という枠組みであり、ようするにアメリカの戦争に協力しているということである。広義の有事法制と狭義の有事法制とを組み合わせると、イラクやインド洋でアメリカに協力している自衛隊に攻撃がくわえられれば、「武力攻撃のおそれ」と認定され国内の有事体制が発動されてしまうという巧妙な仕組みとなっている。つまり、現在の「有事法制」とは、専守防衛のために国内体制を整備するのではなく、アメリカに協力する自衛隊のため国民を動員できるという体制になっている。これはまさしく、憲法が禁止している集団的自衛権である(なお、個別的自衛権については学者の間で議論あり)。
(4)つまり、現段階での有事体制を見てみれば、専守防衛のための明文改憲が必要だという議論は完全に間違っており、現在改憲が行われれば、まちがいなく集団的自衛権(つまり、アメリカの戦争に日本が荷担できる体制)を規定するにきまっている。
こうしたアメリカと一体となった戦争体制の整備は、多国籍企業化した財界の要請(企業の投資を守る等)であり、アメリカの要請(世界支配)となっている。そのため、色々な言い回しはあるものの、自民、公明、民主各党ともに改憲論を唱えるようになている。とりわけ民主党は、改憲の中間報告をまとめるなどの最先端を行っており危険である。
(5)以上のとおり、現在の改憲論は、自公民や財界、アメリカのいうようなものではなく、素朴な気持で「専守防衛」が必要だという国民の考えは完全に裏切られる。国民には、現段階での有事法制を理解してもらうとともに、同時多発テロに対する報復戦争、イラク戦争、北朝鮮脅威論について今一度冷静に考えてもらい、アメリカと一緒に侵略戦争に荷担する危険性を認識してもらう必要があるのではないか。
国民は、集団的自衛権の行使や侵略戦争を望んでいるわけではなく、明文改憲が今まで行われてこなかったのは国民世論の反映であることを考えて運動を広げていくべきである。
(6)(質疑応答)改憲派は、新しい人権などを改憲の目玉に据えたりするが、そうした前進は、べつに改憲でなくても対応できるはずである。環境権やプライバシー権は、裁判闘争によって認めれられているし、漠然とした憲法条文を作るよりしっかりした基本法を制定することを目指すことが大切ではないか。
2 総会議案書の討議
(1)情勢(白子事務局員)憲法が危ない!、年金が危ない!、教育が危ない!、雇用・生活が危ない!という4つの「危ない」動きについて報告があり、いずれも重大局面にあり、民法協の設立趣旨にてらして運動を展開していかなければならないとの報告があった。
「司法改革」の流れの中で、裁判所内に、労使の審判員が加わって個別労働事件を審理する労働審判制が設置されることになったのには前進であり、これを実効性あらしめるためには、これにふさわしい審判員の選出が重要な課題である。
(2)活動報告(増田事務局長)組織活動として、民法協ニュースが、一部の事務局弁護士の負担になっていること、また原稿滞納も一掃できないでいることが報告され、毎月発行を目指したいとの報告があった。また、シリーズ「労基法を使おう」の製本化も作業が遅れていることが報告された。
学習活動は、概ね例年どおりの行事を設けたものの、権利講座では神戸出席者が極端に少なかったこと、出前講座が活発に利用されたとはいえないことが明らかになった。こうした学習活動は、運動の力にもなることから、もっと力を入れることが必要である。
前年度は特に、いままで手薄になりがちだった公務員労働者の労働条件について、独立行政法人や臨時非常勤職員問題の学習と会員組合を中心とした公務職場の実情に関する聴き取りを重点とした。
地労委選任問題は、第37期委員訴訟は1新神戸地裁で判決が言い渡され、一部重要な事実認定があったものの結果として敗訴したことから、直ちに控訴し、舞台は大阪高裁に移っている。これと同時に、第38期委員訴訟、第39期の労働者委員選任をめぐるシンポジウムなどを積極的に行っている。
また、川重賃金差別(地労委)、新日鐵広畑賃金差別(訴訟)という賃金差別裁判で勝利を収めた重要な成果が報告された。
(3)会員組合からの活動報告○全日検:第2次裁判についての取り組みが報告された。
○宝塚映像:中労委へ裁判闘争の舞台を移した現状について報告された。
○川崎重工争議団:画期的な地労委命令にもかかわらず、川重が抜本的解決に背を向けており、運動を強化していくことが報告された。
○新日鐵争議団:本年3月、地裁姫路支部は会社の反労務政策を認め慰謝料の支払いを命じたが、会社は不当に控訴。公正裁判を求める署名にご協力を、と報告された。
(4)活動方針以上の活動報告を踏まえて、学習活動の強化、個別紛争への民法協の取り組み、地労委問題、憲法問題への取り組み強化の方針を採択した。
(5)和田邦夫代表幹事の退任あいさつ本総会をもって、長年代表幹事を務めてこられた和田邦夫さん(私教連)が退任することとなり、和田さんからのご挨拶と、会からの記念品贈呈が行われた。
このページのトップへ選手会ストライキに思う
「あっぱれ古田!!」
弁護士 増田 正幸
1.はじめに
労働組合日本プロ野球選手会(以下「選手会」という)が大阪近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブの間の営業譲渡に関して2004年9月18日及び19日にストライキを敢行し、9月23日には選手会と日本プロフェッショナル野球組織(NPB)との間で、新規球団の加入を募って12球団2リーグ制の維持に努めることやNPBと選手会の間でプロ野球構造改革協議会を設けてドラフト改革、選手年棒の減額制限の緩和などについて協議することなどを合意した。
選手会のストライキに関しては連合が表に出ない形で全面的に支援し、全労連など他の労働団体も署名活動などで支援した。
「ストライキ」が行われなくなって久しいが、こんなに多くの市民が応援するストライキも珍しい。そして、選手会の活動によって、私たちはあらためてプロ野球選手も労働者であること、労働者には団結権・団体交渉権・争議権という武器が与えられていることを再認識した。
そこで、選手会のストライキをめぐって労働組合法上の何が問題となっているかを以下に整理した。
2.選手会は労働組合といえるのか
(1)労組法2条は労働組合を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体またはその連合団体をいう」と定義している。すなわち、労働組合は「労働者が主体」となることを要件としている。
「労働者」について、労組法3条は「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義づけているにすぎない。
「賃金、給料その他これに準ずる収入」という文言だけでは基準として明確でないので、学説判例は「労働者」か否かを「使用従属関係」の有無によって決めている。そもそも憲法28条が団結権等を保障したのは、使用者に対して従属的な地位にある者が、団結権等の行使を通じて相手方と対等な関係に立ち、労働条件決定に実質的に関与しうることを保障するためであると解されるからである。
「使用従属関係」とは、| (ⅰ) | その者が当該企業の事業遂行に不可欠な労働力として企業組織に組み込まれていること |
| (ⅱ) | 契約の内容が一方的に決定されること |
| (ⅲ) | 業務遂行の日時、場所、方法などにつき指揮監督を受けること |
| (ⅳ) | 業務の発注に対し諾否の自由がないこと |
等のいくつかを備えるものとされている(菅野)。
(2)プロ野球界には年俸1億円を超える選手が74名もいるし、毎年選手が個別に会社と交渉して賃金(年俸)を決め、契約を更新する姿が報道されているが、果たして、プロ野球選手は「労働者」といえるのだろうか。
①各球団は、ドラフト制度で交渉権を獲得した新人選手やドラフト会議で指名されなかった選手と個別に契約交渉を行い選手契約を締結する。ただし、交渉対象となるのは契約金及び参稼報酬額(「年俸」)であって、その他の契約条件についてはセ・パ両野球連盟とその構成球団により結成された日本プロフェッショナル組織が作成した日本プロフェッショナル野球協約(「野球協約」)と統一契約書によって画一的に定められ、野球協約及び統一契約書に反する選手契約の特約条項は無効とされる。
②野球協約によれば、球団と選手との間の選手契約が連盟会長の承認を受けることにより、選手は球団の支配下選手となる。
③球団は、毎年11月30日までに支配下選手の内、次年度の選手契約締結権を保留する選手(契約保留選手)の名簿を提出する(70名以内)。
契約保留選手は、その翌々年の1月9日までの保留期間中に契約を更新することになるが、その間は他球団との契約は一切できないし、保留期間の途中で任意引退をしても球団がコミッショナーに自由契約選手とする申請をしない限り他球団と契約することもできない。
逆に、保留期間中はいつでも他球団への契約譲渡(トレード)の対象となる。
④契約保留選手が球団との交渉がまとまらず球団が放出(解除)を決めた場合は、連盟会長宛に他球団に譲渡の請求を求める手続(「ウェイバー公示」)取り、譲渡請求があれば契約上の地位を譲渡することになる。
どの球団からも譲渡請求がなかった場合や契約保留選手の名簿に登載されなかった選手は自由契約(フリー・エージェント)選手となり、他球団との契約が可能になる。
⑤野球協約や統一契約書の変更及び廃止は両連盟会長及び各球団の代表によって構成される実行委員会が行うことになっているから、選手は年俸以外の労働条件はNPBが一方的に作成する野球協約や統一契約書に拘束される。
⑥このようにプロ野球選手の契約内容は一方的に決定されており、いったん支配下選手(契約保留選手)となると、まさに球団の完全な「支配」の下に置かれ、他球団との契約は禁止され、成績不振になればいつ解雇されるか、トレードに出されるか(統一契約書ではトレードされた場合のトレード先への4日以内の出頭義務と遅れた場合の制裁金の支払まで決められている)がわからないという不安定な地位に置かれており、文字どおり球団の「支配」下に置かれているから、球団との間で使用従属関係にあることは明らかである。
⑦プロ野球12球団の支配下選手は2004年度は1・2軍合わせて751名、開幕日に1軍登録されたのは289名である。
2004年度の支配下選手の年俸は下表のとおりであり、1000万円未満が37.3%、2000万円未満は58.5%であって、選手の技能や費やされた努力、及び選手生命の短さなどを考えると、決して恵まれているとは言えないのが実情である。
| 500未満 | 500~1000 | 1000~2000 | 2000~3000 |
| 39人 | 241人 | 159人 | 85人 |
| 5.2% | 32.1% | 21.2% | 11.3% |
| 3000~5000 | 5000~7000 | 7000~1億 | 1億以上 |
| 72人 | 47人 | 34人 | 74人 |
| 9.6% | 6.3% | 4.5% | 9.9% |
(3)したがって、プロ野球選手も「労働者」として労働組合を結成する権利を有することになる。実際に、選手会は1985(昭和60)年11月5日に東京都地方労働委員会において労働組合法上の労働組合として認定されているから、選手会が労働組合であり団体交渉やストライキなどの争議行為を行う権利があること及び不当労働行為救済制度を利用できることには疑いの余地がない。
そして、現在は日本人のプロ野球選手全員が選手会に加入している。
3.団体交渉の相手方は誰か。
個々の選手が選手契約を締結している相手方である各球団が「使用者」として団体交渉の相手方となることは当然である。
選手会は全球団の横断組織である。
また、前記のとおり、選手の労働条件の多くは野球協約と統一契約書で定められているのであるから、各球団を団交の相手方とするだけでは不十分である。
「使用者団体」も団体交渉を意義あらしめる程度の統制力を備え、かつ定款または規約でそれを予定している場合には団体交渉の当事者となりうる。
ところが、NPBは各球団を構成員とはしているが、それ自体が構成員のために統一的に団交をなし、かつ労働協約を締結することは予定されていないので、使用者団体として団体交渉の相手方にすることはできない。また、コミッショナーには選手の労働条件の決定権限はないのでコミッショナーも相手方とはなりえない。
これに対して、各球団から野球協約と統一契約書の変更権限を付与されているのは「NPB実行委員会」であるから実行委員会が団体交渉の主要な相手方ということになる。
4.球団統合は団体交渉の対象となるのか。
(1)団体交渉でいかなる事項を取り上げるかは交渉当事者が自由に決める事柄であるが、使用者が団体交渉を行うことが労組法によって義務づけられる事項(義務的団体交渉事項)がある。義務的団体交渉事項について使用者が団体交渉に応じなければ団交拒否の不当労働行為ということになる。
(2)義務的交渉事項とは、労働条件など労働者の経済的地位に関係があるかもしくは労働組合そのものに関係ある事項で、かつ使用者の処理権限に含まれる事項である。
ところで、しばしば、使用者は経営・販売戦略、役員・管理職の人事などは「経営権」事項(ex.新機械の導入、設備の更新、生産の方法、工場事務所の移転、経営者・管理職の人事、営業譲渡、会社組織の変更、業務の下請化)で、使用者が自らの責任で決定すべきことであるから団体交渉になじまないと主張する。
しかし、これらの事項でも労働者の労働条件や経済的地位の向上と関係がある限りは義務的交渉事項になる。たとえば、新たな生産方式の採用や機構改革などは従来の労働のあり方を変え、労働者の雇用、労働時間、労働強度に大きな影響を及ぼすし、本件のような球団統合(営業譲渡)も同様である。
(3)選手会と古田選手(選手会長)、礒部選手(大阪近鉄)、三輪選手(オリックス)の4者は、2004(平成16)年8月27日にNPB、大阪近鉄、オリックスの3者を相手方として「営業譲渡及びそれに関する労働条件について団体交渉を求めうる地位にあることを仮に定めること」、「NPBが両球団間の営業譲渡及びそれに関する労働条件について特別委員会を招集し、その議決を経ない限り審議議決しないこと」、「両球団間の営業譲渡差止め」などを求めて東京地裁に仮処分申請をした。
東京地裁は9月3日に選手会側の申立てを却下し、選手会の即時抗告申立てに対し9月8日に東京高裁もこれを棄却した。
東京地裁も同高裁も選手会に団体交渉権があることは認めたが、地裁が球団統合(営業譲渡)に伴う労働条件に関する事項は義務的団体交渉事項に該たるが球団統合(営業譲渡)自体については義務的団体交渉事項とは認めなかったのに対して、高裁は、球団の統合(営業譲渡)自体についても選手の労働条件に係る部分は義務的団体交渉事項に該当することを明確に認めた(なお、裁判所は相手方が団体交渉に応じており、今後も応ずる意向を表明していること、相手方代表者のコミッショナーが法律家であること等を考慮して保全の必要性がないと判断したものである)。
(4) 本件ストは、この間行われてきた団体交渉の経緯をふまえ、最終的には、9月16日、17日の団体交渉の結果にもとづいて実施された。上記団体交渉において、選手会は、①合併の1年延期が無理な場合、新規参入を促し、来季からセ・パ各6球団を実現すること、②合併の際の選手の移籍に対してプロテクトの対象から外し選手の意見を尊重することなどを要求した。これに対してNPB側は、①合併の延期はできない、②来季は時間的制限もあり、セ6球団・パ5球団とする等を主張し、交渉は決裂したと言われている。
①の要求は、経営事項に関わる問題を含むものではあるが、新規参入を求める点は、選手の「雇用の場」の確保という面から、雇用・労働条件に密接に関連する問題であり、また②の要求は、まさに雇用条件そのものに関する問題にほかならないから、いずれも義務的団体交渉の対象事項というべきは明らかである。
5.選手会のストライキに対して球団は損害賠償請求ができるか。
(1)選手会のスト表明に対して、複数の球団オーナーがマスコミを通じて損害賠償請求をする意向を明らかにしている。
しかし、選手会は労働組合であり団体交渉権、争議権を有する。前記のとおり、球団統合についてもそれが組合員である選手の雇用や労働条件に大きな影響を及ぼすことから義務的団体交渉事項に該当するがゆえに、球団統合に関する選手会の要求が容れられない場合にはストライキを行う権利を有する。
そして、ストライキが正当な目的のもとに正当な手段で行われる限り、労働者及び労働組合は使用者から損害賠償責任を追求されることはない(労組法8条)。
選手会が球団統合問題に関して争議を行うことは一面では球団経営への干渉を目的としているということができるが、しかし、そのような干渉を通じての労働者の経済的地位の維持、向上が目指されていることが明らかである以上、今回の選手会のストライキは義務的団体交渉事項に関するもので、目的において正当な争議ということができ、争議権濫用に該たらないことは明らかである。したがって、球団側は選手会に対して損害賠償請求をすることはできない。
(2)なお、この点について、2004年9月7日付けの毎日新聞紙上において、兵庫県地労委の公益委員でもある小嶌典明大阪大学教授は、以下のとおりコメントしている。
「東京地裁は仮処分申請で選手会を『団体交渉の主体となり得る』と判断した都労委も同様の判断を過去にしており、労働組合と認められているからストライキを行うことは可能だ。一部の経営者の『選手会は労組ではない』という主張は認められない。だが、地裁は選手の労働条件に関する団体交渉権は認定したが、営業譲渡問題は『義務的団交事項』に当たらないと判断している。営業譲渡は、経営者側が決めるものであって営業譲渡を理由としたストに対して日本プロ野球組織(NPB)が損害賠償請求をした場合は認められる可能性は高いだろう。『営業譲渡反対』を打ち出す選手会の気持は分かるが、労働法上特例扱いにはならないだろう。」
しかし、小嶌教授が営業譲渡問題を義務的団体交渉事項ではないと考えているのであれば、前記のとおり、それは正しくないし、現に東京高裁は営業譲渡問題を義務的団体交渉事項に該たると判断している。それゆえ、「損害賠償請求が認められる可能性が高い」などとはとてもいえないのではなかろうか。
(3)本件ストにおいては、大阪近鉄及びオリックス間の営業譲渡の延期が問題とされており、両球団支配下選手以外の選手がストライキを実施することは、他球団における労使紛争に対するいわゆる同情ストとして正当性がないとの議論もある。
しかし、本件ストは全球団の選手を構成員とする選手会と全球団から委任を受け全球団を構成員とする協議・交渉委員会との交渉の決裂の結果、行われたものである。
すなわち、各球団は、協議・交渉委員会のメンバーであり、本件スト要求にかかわる事項についての決定に関与し、その権限を行使しうる立場にあるばかりか、両球団の統合は全体として選手の雇用の場の縮小をもたらし、両球団の選手の移籍に伴い他球団の選手の雇用・労働条件にも影響を及ぼすから、全球団所属の全選手の雇用・労働条件に密接に関連するものといえるのであって、本件ストがいわゆる同情ストに当たらないことは明かである。
(4)逆に、損害賠償請求の余地がないのに選手会のスト表明に対して、球団側が損害賠償請求の意向を表明したことは、反組合的言論として支配介入の不当労働行為の余地がある。
使用者にも表現の自由が認められており使用者が労働組合のあり方について一般的に見解を述べることが否定されることはない。しかし、使用者の言論は従業員に与える影響が大きいので、使用者の言論が組合の結成、運営に対する支配介入にわたる場合には不当労働行為として禁止の対象になる。
判例は、団体交渉が決裂しストライキを目前にした段階で社長名「ストのためのストを行わんとする姿にしか写ってこないのは甚だ遺憾」「会社も重大な決意をせざるを得ません」等と発言した事案について、「言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入になる」(最判昭和57年9月10日プリマハム事件)としている。
したがって、ストライキ直前にオーナーがストライキの不当性を広くマスコミを通じて訴え、かつ巨額の損害賠償請求の意向を示すことは、組合員に対する威嚇効果を有するものとして不当労働行為に該当するおそれがあるのである。
6.最後に
今回のストライキが成功した大きな要因として、選手会が全球団を越えた横断的組織であったこと、選手全員が組合に加入していたこと、日常的に一方的なトレードや自由契約の脅威にさらされ、不安定な地位に置かれている選手が大阪近鉄、オリックスの2球団だけではなく我が身にも降りかかることとして危機感を抱き一糸乱れず行動したこと等があげられる。
何より、選手会が横断的な産業別組合であるため企業別組合にありがちな「ストライキは会社をつぶす」という恫喝に屈することがなかったということが大きい。
その意味で、「今回の動きは、企業の枠を超えた労組の横断的な行動と、それを可能にする組織作りの必要性を多くの人に痛感させた」(慶應義塾大学樋口美雄教授)ということができる。
このページのトップへ幹事のつぶやき
プロ野球選手会のストライキについて
| JMIU甲南電機支部 野口郷志 |
| 今回のプロ野球選手会のスト及び団体交渉の報道で労働組合の活動が、一般の人にもある意味理解が得られたのではと思う。今回は選手会と言う労働組合があったからこそ、ストライキによる2試合減となったが、球団側の一方的な球界再編とはならずに、選手及びファンの声を聞く団体交渉が行われ選手とオーナーとの合意、新規参入が容易に出来るようになったのではないかと思う。
前巨人軍オーナーの『選手ごとき…』との発言があったが、この発言はまさに経営者が選手を一使用人としか見ておらず、一般の企業でも労働組合がなければこのような団体交渉は行われずに一方的に、選手の権利もファン無視で決められていたはず。選手会も構成する選手の個々の労働条件(1軍と2軍の選手、年俸)の異なる中でストライキ決行を良く決められたと思う。今後の合併に伴う選手のリストラ、新球団発足により選手へのしわ寄せが来るが、選手会と言う労働組合の活動に注目したい。 |
| 吉原製油労組 綱本 勝 |
| “ストライキ”決行と言うことで、ファン(客相手)があってこそと言われる中では、正直な処、①良く決行した。②合併・リストラとなればやむをえないかと思う又、ゲームを見る楽しみよりも、ストライキを支持した野球ファンが多かったのもうなずける(私もその一人)。過去に2~3軍選手の待遇年俸(最賃!)をめぐって紛争になりそうになった事が思い出された。経営側の都合で、一方的な球団売却等のあり方は、民間の経営統合や合併のロケーションとダブってくる。銀行や大企業の労働者は、同様の立場のところもあるだろうが、ストライキの声すら出ない。元気をだしたいものだ。 |
| 東熱労組 鈴木義一 |
| 米今回の問題は、近鉄とオリックスの合併問題をプロ野球選手会がプロ野球全体の問題として交渉した事に意義があり、近鉄・オリックスの選手会のみの交渉だと近鉄と言うチームが消滅するだけで終わって、球界全体の問題まで発展しなかったと思う。ストについては思い切ってよくやったと思う。ストライキの影響は大きいと思うが、しないと問題解決しなかったと思う。プロ野球選手会は労働組合で見ると、産別の組合であって単組のみの交渉ではなく、同一産業分野での闘いが大きな成果を得ると思われる。 |
| 神戸交通労組 須多正裕 |
| オリックスと近鉄の合併に端を発した今回の選手会ストライキについて、経営上の問題とは言え、プロ野球ファン・選手を無視した今回の経営陣の暴挙?は、プロ野球ファンの一員として許されざる行為であったと思います。
子供達の夢を壊す等、ストの是否については賛否の分かれるものではありますが、大半のプロ野球ファンの方達と同様に、今回のストに対しては好意を持って見守っていました。 神戸交通は、市バス・地下鉄の職員で組織する組合で、オリックスの本拠地であるヤフーBBスタジアムの最寄り駅の総合運動公園は市営地下鉄の駅でもあり、両球団の合併により乗客が減少するのは本当に痛いです。当労組でも新球団?の本拠地が「神戸」に残るよう署名活動を取り組みましたが、最終的には大阪に行ってしまうかなぁ…。 |
| 兵庫私教連 森本 英之 |
| プロ野球選手会の“スト”は、ストライキという言葉とその意味を甦らせ、若者へもアピールした。事実、家の小2の子どもが「ストってなあに?」とたずねてきたので、これ幸いと丁寧に答えておいた。こういう事が、全国で起こっていないかと期待しているのだが…。一挙手一投足まで、小さな時から監督の指示に従ってやってきた選手達が、人間としての尊厳を主張したターニングポイントの出来事だと考える。30代や40代のIT企業が球団を所有すれば、また違った結果が表れるだろう。歴史の歯車はやはり、少しずつ廻っているんだ。 |
| ガーコのひとりごと | |
| 7月23日に開催されました「なんで『連合』だけやねん!part2」シンポジウムに参加させていただきました。愛知県・福岡県の画期的な判決内容を勝ち取られた経験についてシンポジストの原田さん・久間さんよりご報告をしていただきました。また、兵庫県訴訟に続き神奈川・京都が訴訟の準備に入っているので、今後他県との連携も重要であるなどの助言もいただきました。私自身まだまだ地労委についてわからないこと・知らないことが沢山あり、もっともっと学習しなければいけないと痛感しました。文字どおり「労働者のための」地労委にするためには、一つ一つの運動の成果を積み重ねることが必要ではないかと思います。1日も早い公正な任命が必ず実現するために、皆さんのご支援をお願いいたします。 |
|
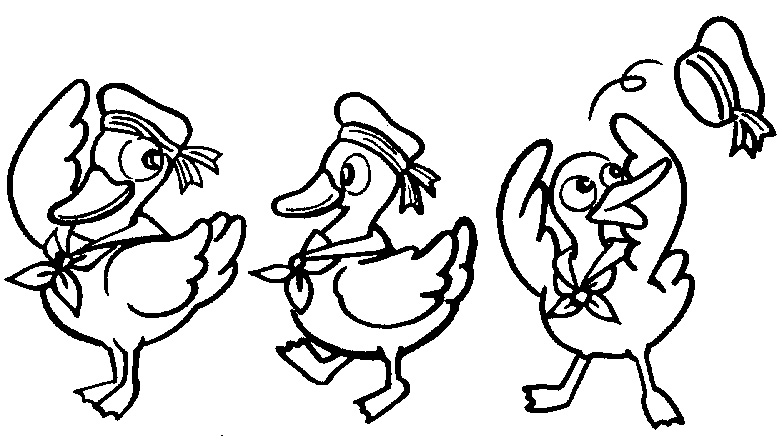
このページのトップへ